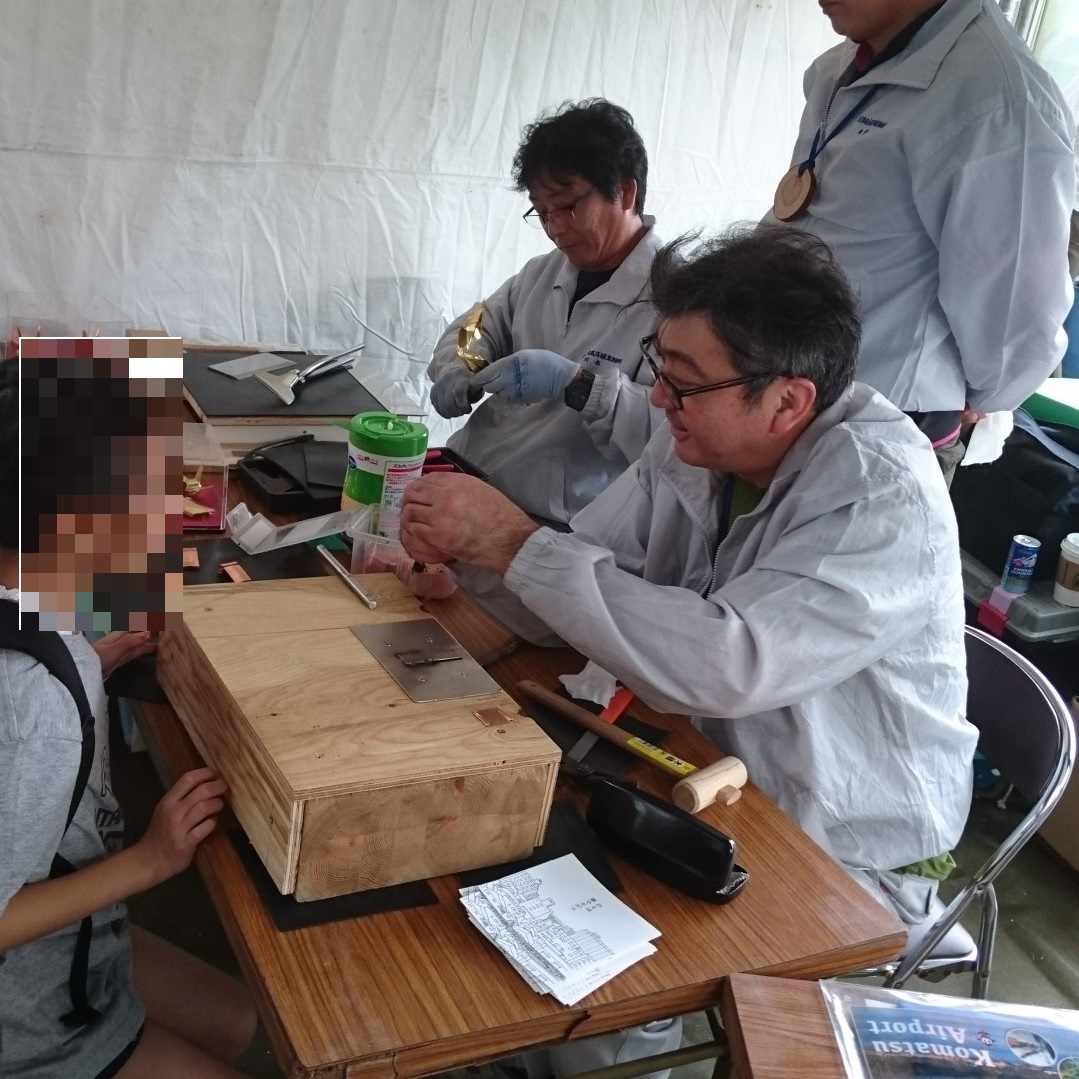8月3日に行われたJERCO((社)日本住宅リフォーム産業協会)主催による勉強会に参加。メインテーマは『性能向上リフォームの現地調査・インスペクションを徹底的に知る』となっているが、前回に続き雨漏りに関しても勉強。
第1部 ㈱日本住宅保証検査機構 田村さん
保険事故(新築、リフォーム共)の1番の原因は雨漏り(新築:93.9% リフォーム:90%)で、保険事故を起こした屋根形状の割合は片流れ:43% 切妻:25% 寄棟:12%になり、雨漏りを防ぐ事が事故の防止につながると。
第2部 ㈱LIXIL 鷹取さん
一部屋単位から手軽に断熱リフォームできる素材『エコエコ』を開発発売したとの説明。今ある壁・床・窓を利用し、工期期間最短1日と住まいながら出来きるとのこと。加えて支援補助金事業の対象商品でもある事から、断熱リフォームを躊躇うお客様への提案も行いやすい商品であると。
第3部 (一社)住まいの屋根換気壁通気研究会 神戸さん
「雨漏り結露が原因で家の耐久性が損なわれる」と熱弁。住宅が高性能化しているが、必要な換気や通気を考えずに高断熱化高気密化しているので、結露事故とそれを原因とする構造材の腐敗事故が増加している。雨水を建物内部に侵入させずに換気(通風)を行い結露を防ぐ事が大事であると。
第4部 アーキヤマデ㈱ 西田さん
主に公共建築物やオフィスビル、工場の屋根(屋上)の再断熱防水に関してのお話し。既存の屋根(屋上)に合わせた再防水の工法(塗り、貼り、留める)が有るが、これからの断熱防水として、劣化を招く内部結露を防止ししながら(強制換気)、夏季・冬季の温熱を考慮した工法を提案していくのが良いあと。
第5部 i-sumu設計㈱ 荻野さん
インスペクション(現地調査)を行うに当たっての、調査前(準備)・調査時・調査後(事務作業)のノウハウを役職者である荻野さんの観点から伝授。適切なインスペクションを行うには社員のやる気が大事と、調査時のユニフォームを提供し、お互いにフォローする体制が必要と二人一組でないと調査を行わず、調査時の7つ道具はアイデアが満載である。煩雑になりがちな調査後の事務作業(報告書)は能率を重視しアプリを多数活用。肝心の“調査”であるが、手を抜かず隅から隅まで目を通す事(調査)は勿論、分からなければ机上(書物)も活用し経験を積む事が大事であると。
最終講話者のi-sumuの荻野さんが、今までのお客様と担当した社員たちの写真を映像にし講話を閉められた。映りだすお客様と社員たちは必ず“笑顔”でいる。荻野さんのキャッチーは「お客様の笑顔の為に」だそうだ。荻野さんの思いが社員たちに伝わり、社員たちがお客様を笑顔にしている、良い“写真”。
そして、おそらく荻野さんだけじゃなく、壇上に立たれた講話者達も、同じ場所でその話しを聴いていた人たちもお客様の笑顔を見たいと思って研鑽しているに違いないと思った。
わたなべ きょうこ